Interview vol.01
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
取締役 人事総務本部長
島田 由香 Yuka Shimada
「WAA」(Work from Anywhere and Anytime)など、それぞれの従業員に合った新しい働き方を推進しているユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長である島田由香さんに、「ワーケーション」の価値や可能性についてお話を伺いました。
インタビュー:KomfortaWorkation 山根好子

Interview vol.01

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
取締役 人事総務本部長
島田 由香 Yuka Shimada
「WAA」(Work from Anywhere and Anytime)など、それぞれの従業員に合った新しい働き方を推進しているユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長である島田由香さんに、「ワーケーション」の価値や可能性についてお話を伺いました。
インタビュー:KomfortaWorkation 山根好子
『新しい働き方』と『ワーケーション』について
―まずは、働く場所・時間を社員が選べる、御社の「WAA」の考え方について教えてください。
「WAA(Work from Anywhere and Anytime)」はその名前の通りどこで働いてもいいし、いつ働いてもいいという制度です。
実はとても愛を込めたネーミングなんですよ!1つは、「わぁ!」という、楽しいこと・驚きがあった時の感嘆の声を掛けています。どうしても仕事に対して、苦しい・歯を食いしばる・修羅場というようなイメージを持つ人が多いのですが、私はそうは思っていなくて。「仕事は喜びを見つけていくプロセスである。楽しい驚きがあるのが仕事だ」というメッセージです。もう1つは、このような取り組みが「ワーッ」と勢いよく広がっていくようにと考えてつけた名前です。
―なるほど!ただの制度ではなく、働き方自体への強い想いがこもっているんですね。
はい。「WAA」は、ただの制度ではなくマインドセットやスピリットです。結果さえ出せば、いつどこでも働いていい。いい気持ち――ウェルビーイングが高いときに一番いい結果を出せるというのは組織心理学でも実証済で、“会社に言われるがまま場所や時間に縛られて働く”という呪縛を解くためのものと考えています。
また、会社にどうあってほしいかというメッセージ的な側面もあります。やり方のDoingではなく、あり方のBeingを大切にしてほしいという挑戦でもあるんです。

―「新しい働き方」の制度についての話題になると、社内から「できる人とできない人がいて不公平だ」という声が出てなかなか導入を進められないという声をよく耳にします。実際、導入にあたってそういった声がハードルになりましたか?
そもそも、平等・不平等ってなんでしょう?「すべての人に同じことをする」=「平等」と思い込んでいる人がいるように思います。でも実際にはそうではない。みんな違う仕事で、みんなに違うニーズがあるからです。
例えば、3人の人がいて、私が全員に同じ飴を配ったとしますよね。でも本当は、Aさんはバナナが食べたい、Bさんはハンバーグが食べたい、Cさんに至ってはコーヒーが飲みたかったかも。そうすると、「みんなに同じ飴を配れた」と満足しているのは私だけです。全員に同じことをするよりも、一人ひとりのニーズをどう満たすかが大事です。
「WAA」を導入したとき、初めはすべての業務で導入できると仮定しました。ふたを開けてみると、やはりどうしてもできないのは工場のオペレーターの方の業務でした。オペレーター業務は仕事の場所と時間が決まっていて、その場を離れて仕事ができません。でもエンジニアなど、工場の中でも「WAA」ができる人がいました。そういうメンバーは実際に「WAA」を活用できるようにしています。
―同じ工場勤務でも、職種によって対象になるんですね。
もちろん、これに対して「不公平だ」という声もありました。でも、不思議なことにその声は工場の中からは出なかったんです。工場の外の人の、優しさからの声だったんですね。
実際の工場のニーズはカレンダー通り・予定通りに仕事ができること。だから「WAA」ができないメンバーには、彼らのニーズを満たすためにできることを考える。そうすればそれぞれのニーズを満たすことができます。
―本当の意味で平等になれば、当事者からは不公平感が出ないんですね。
やさしさからの「不公平ではないか」という声だった、というのは目から鱗です。
より多くの企業が同様に新しい働き方――ワーケーションなどを当たり前の働き方にするためにはどうしたらいいと思いますか?
「できない」というのは、厳しい言い方だけど言い訳じゃないかなと (笑)
やりたかったらできる。本気で変えようとしていないだけ。本気でどうやったらいいか考えていくと、必ずソリューションが出てきて、それを応援してくれる人が出てくるんです。
実際に、「ユニリーバだからできる」「島田さんだからできる」と言われることもあるけど、違うと思う。みんなできることだから、本気で取り組むかどうかだけの違いだと思います。
『ワーケーション』の価値と、もたらす未来について
―島田さんはご自身でも積極的にワーケーションをなさっていると思います。
実践してみて感じたことや気付いたことを教えてください。
「私が思ってた通りだった!」というくらい、”場所が変わる”ことへの意味や価値についての確信を日々深めていっています。人間は、環境にものすごくインパクトを受ける生き物です。視覚に何が入ってくるかで脳の動きが変わるんですよ。例えば、脳科学でわかっていることの1つに、「何かを覚えたいときは、いつもと違うところで勉強するとよい」ということがあります。視覚情報から、脳が「いつものところじゃない!」という危機を感じて活性化することで、記憶に残りやすくなるわけです。同様に、自然・グリーンが視界に入ると前頭葉が活性化することもわかっているので、自然があるところで行うことも多いワーケーションでは、脳が活性化すると言えますよね。
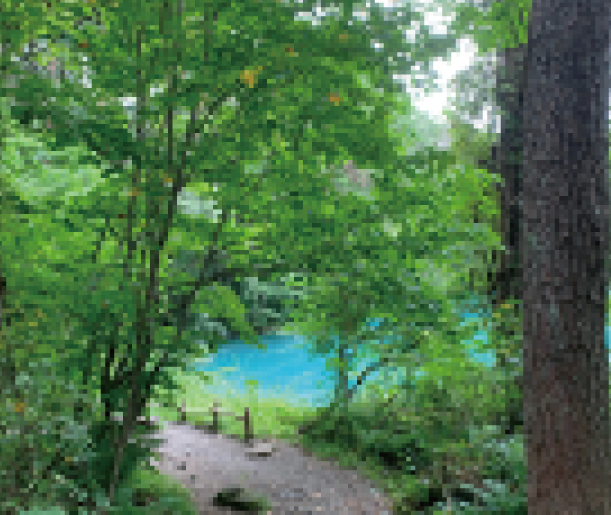
―科学的にもワーケーションで脳が活性化するんですね。
実際、私も体感したんですよ。3月18日から7月20日まで、自粛生活でほとんど外に出ていませんでした。そんな中、どうしても必要になり沖縄に行くことになって…沖縄に着いた途端、目の焦点が合わなくなっている自分に気づいて、びっくりしちゃいました。ずっと家で在宅勤務を続けていて無意識に見ていたのは家の壁だったのが、突然、青い海・広い空・やんばるの緑が目に飛び込んできて、どこを見ていいかわからなくなってしまったんですね。その時は本当に自然のエネルギーを全身で感じて、これが自分の生きるエネルギーなんだ!と気づきました。
この経験があって、ずっと家にいると気づかないうちにウェルビーイングは失われていっていることがわかったので、そこからは意識して外に目を向けるるようになりました。
―私(山根)も最近は毎週のようにワーケーションしているので、とても共感します。これまでは営業や出張に行くたび色んなものを五感で感じて、無意識のうちにインプット出来ていたのに、今は自分で意識してインプットしにいかなくてはいけないと感じています。
自分は在宅で大丈夫と思っている方にもワーケーションを体験してほしいです。
そう思います。ワーケーションをすることで、会社で「なんであの人だけ」と言われることもあるかもしれないけれど、明確に「やってはだめ」という決まりでもないなら、誰でもやっていい。ワーケーションをする=自分で働く場所を選択しているだけだから。
私の場合、恵まれていると思うのは、上司――社長が私のことを理解してくれていることかな。私がどうあると一番調子がいいかわかってくれているから、感染防止策のような安全面での条件を満たせば、ワーケーションを選べるようにしてくれています(笑)。ワーケーションができる環境かどうか、というよりも私自身が働く環境を選べるという『選択肢』が広がっていることがいいんです。それが私のパフォーマンスにつながるから。

―だんだん、島田さんの思うワーケーションについて理解できてきたような気がします。
ずばり、島田さんの思う「ワーケーションの価値や働くことの未来」について教えてください。
政府が本格的に「ワーケーション」という言葉を使い始めたのは、今年(2020年)の7月27日。当時の菅官房長官が言い出したところからだと記憶しています。民間ではもっと前から、旅行業者が「ワーケーション」「ブリージャー」などの言葉を使っていたけれど、この政府の発信から一気に「ワーケーション」という言葉が広がっている。みんなが注目するようになって、とてもいいことだと感じています。
私は、ワーケーションは、日本の国力を上げていくものだと思っているから、全身全霊で進めていきたいんです。
―国力ですか?!
そう。一人ひとりがまだ出していない可能性・ポテンシャル・能力を開花させるきっかけになると考えています。呪縛から解かれるというか。「○○しなくてはいけない」ではなく、自分軸でモノを考え、選んでいくことに繋がるから。
―先ほども「呪縛」「選択」というキーワードがありましたね。
というのも、日本社会には自分で決めるということをしなくなってしまう仕組みがあるように思います。“会社で決められているから“、9-17時で働く、とかお昼は12-13時、とか。そういう発想は違うんじゃないかって。
―自分で一番働きやすい時間や場所を決める、選ぶという考え方ということですね。
それを選べるようになることが、呪縛から解かれると。
はい。そういった「自分で決める」という大事な風潮を醸成できるのが、ワーケーションという取り組みだと思っています。
生き方を選ぶということは、人生を豊かにしていく可能性を含んでいる一つの決断であるとも言えます。「決断」と言いながらも何回でもできる。ワーケーションは1つのアトラクションのようなものでもあります。
日本には素晴らしい場所がたくさんありますよね。せっかく日本人に生まれたのに、それを知らないままなんてもったいない!現地の素敵な人に出会い、これまで知らなかった魅力に触れ、また行きたくなる・また会いたくなる。それを繰り返すと、気に入った場所を仕事の拠点として使うようになったり、移住したり。ワーケーション、という行動は、「自分で働く場所を選ぶ」という気軽にできる選択で、それがいつか移住などの大きな決断につながるものになるんです。

―色んな地域とのつながりが新たにできる――よく「サードプレイス」というような言葉を使いますが、ワーケーションでそれを増やしていくことで、人生の選択の幅が広がっていきますね。
その通り!また、防災対策という観点からも、色んな地域につながりがあることで、何かあった時にお互い助け合うことができるようになります。最近は大きな災害も増えているので、そういった環境においてもたくさんの地域に繋がりを持つことは大切なことだと思います。
―今日お話を伺ってみて改めて、私たちKomfortaWorkation(コンフォルタ・ワーケーション)の掲げているワーケーション「Work×Location×Connection」の考え方や、ワーケーションを通じて体験してほしいことが、島田さんの思うワーケーションや、「地域deWAA」(※地方創生と絡めた「WAA」の取り組みの1つ)と、とても近いように思いました。
そうですね。私も最初にお話を聞いた時、同じ方向を向いているのを感じて嬉しかったです。「Work×Location×Connection」というコンセプトもとても分かりやすく、的を射ていると思います。
「Location」は、日本国内だけでも47都道府県、1,741自治体…ほぼ無限に場所があるけれど、ほとんどの人はそれを”知らない”。“知る”ことで初めて行ってみよう・やってみようと思えるものです。そんな、知られていない「Location」をどんな風にシェアしていくかが大事ですよね。発信を見て知った人に対しては、さらに「行ってみよう」と思わせる何かしらの「つながり」が必要です。その地域や施設に行ってみてできる「つながり」も大事だけれど、知ったときに「これは!」と思う興味関心のつながりがあるから行ってみようと思える。KomfortaWorkationの「Connection」は、そんな物理的なConnectionと、心理的なConnectionの両方のことを言っているのかなと思います。
すごく共感をしています。
————————————————————————————-
島田 由香 氏
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長
1996年慶応義塾大学卒業後、パソナ入社。2002年米コロンビア大学大学院にて組織心理学修士取得、日本GEにて人事マネジャーを経験。08年ユニリーバ入社後、R&D・マーケティング・営業部門のHRパートナー、リーダーシップ開発マネジャー、HRダイレクターを経て13年4月取締役人事本部長就任。14年より現職。「国際女性デー|HAPPY WOMAN AWARD 2019 for SDGs」受賞。高校2年生の息子を持つ一児の母親。米国NLP協会マスタープラクティショナー、マインドフルネスNLP®︎トレーナー。
あわせて読みたい▼
【vol.2】ライオン株式会社 藤村 昌平 様
【vol.3】株式会社イブキ 平井 孝幸 様
【vol.4】株式会社休日ハック 代表取締役社長 田中 和貴 様
【vol.5】アデコ株式会社 コンサルティング事業本部 本部長 増山 辰祐 様/シニアコンサルタント大島 麻由美 様
【vol.6】心臓血管外科医師 奈良原 裕 様
【vol.7】バリュエンスホールディングス株式会社 人事部長 大西 剣之介 様
【vol.8】株式会社スピードリンクジャパン 取締役 太田 可奈 様
【vol.9】AKKODiSコンサルティング株式会社 未来創造グループ部長 種畑 恵治 様
【vol.10】静岡県富士市 産業政策課 課長 岡 利徳 様
NEXT 【vol.11】Coming soon…
▼ワーケーション無料モニター体験も実施中です!
